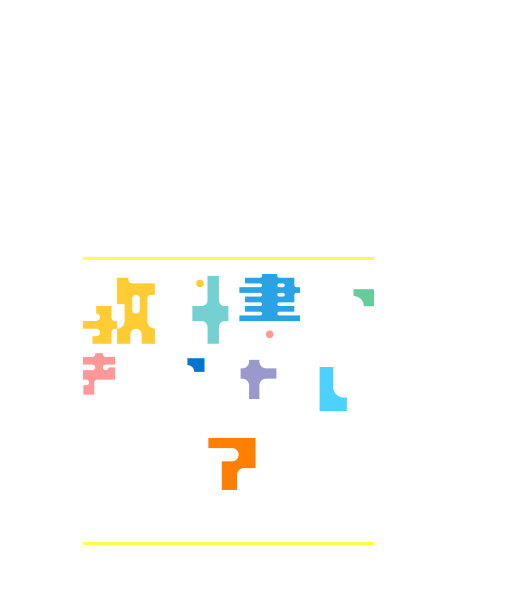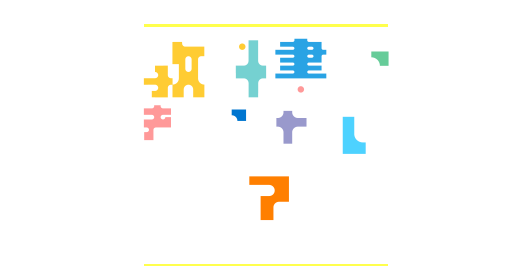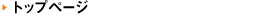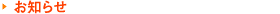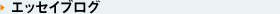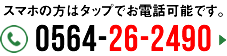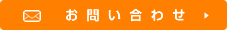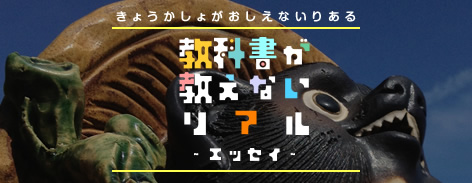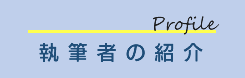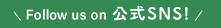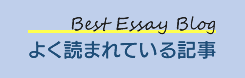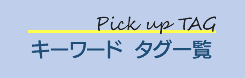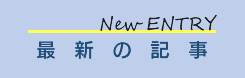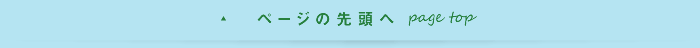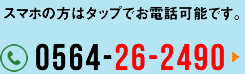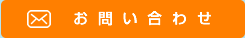15
2018.01
【実話】かまいたちじいさん
これは、完全なる実話。
なのに、なかなか信じてもらえないお話です。( ;∀;)
ガングロ・コギャル全盛時代
僕が高校生だったころ、同年代の多くは黒い肌をしていました。
「ガングロ」という言葉が流行し、男女問わず黒い奴が何となく時代の風潮をつかんでいるように感じさせたものです。
今となっては死語となってしまった「コギャル」(高校生のギャル・子ギャル)も、「こげたギャル」と語源を改めてもよいのではないかと思うほど、多くの高校生が日焼けした肌で誇らしげに街を闊歩していました。
僕は剣道部という室内の部活に所属していたこともあり、ほとんど日光に当たることはありませんでした。
日常生活でハーフパンツなどを履けば多少ひざから下は褐色になることもありましたが、もともと色白であった僕の太ももは、もはや「美白」に近かったと思います。

修学旅行で撮った男子部屋の集合写真は、無駄にみんな上半身が裸でした。笑
それぞれ部活で鍛えた胸筋や腹筋を披露していたのですが、みんななぜか服の下の胸や腹、それに背中までもがいい褐色に染まっているのです。
僕は自分の肌の白さを嘆きました。
いやだ。
僕も褐色のナウい男になりたい。
紫外線に徹底的に身をさらす暴挙
そして、夏休みを迎え、僕は近所の市民プールに出かけました。
日焼けをするためです。
真っ黒になって、2学期を迎えてやる。
ただ、僕は分かっていませんでした。
あまりにも無知だったのです。
日焼けクリームを塗るなどのUVカットをいっさいせず、ひたすらプールサイドに寝転がり暑さに限界を感じたら25m泳いで体をふかずに日に当たる。
それを夕方まで続けた僕の皮膚の遺伝子は、紫外線という見えない恐怖のビームによって完全に破壊されてしまいました。
僕は、両ひざの裏側と、胸の一部がアトピー性皮膚炎と診断されました。
過剰に紫外線を浴び続けたことによる完全に後天的な、そして完治の難しいものを呼び起こしてしまったのです。
幸いなことに、今現在は夏場に異常に汗をかいたりしなければそこまでかゆくはならないし、薬を塗ればかゆみもおさまるくらいの軽度の状態ですが・・・。
皮膚科の待合室
数年前の夏。
連日の熱帯夜で寝苦しい夜が続いていました。
少しずつひざの裏側にかゆみを感じ出した僕は、翌日、近所の皮膚科に行きました。
知識としても経験からも、こういうのはかきむしるとどんどんかゆみが増大し、さらにかいた傷痕が痛みをも伴うようになり、自分で見ても痛々しい状態になっていくものです。
そうなる前に、さっさと病院に行って薬を処方してもらうのが一番です。
夏の皮膚科はとても混雑します。
駐車場は入りきれない車であふれ、小さなコストコ渋滞のようにハザードをたいた車の行列ができていいました。
予約システムがある病院もありますが、このとき僕が行った病院は昔ながらの、待合室で順番が呼ばれるのを待つところでした。
午前9時から診察開始なのだが、車が駐車場に停められそうもなかったので、いったん家に帰り、歩いて再び病院に行きました。
すでに待合室は満員状態で、立って待っている人もいます。
運よく目の前の人がすぐに呼ばれて席が空き、僕は座って待つことができました。
恐怖のじいさん登場
僕が雑誌を読んでいると、何やら独り言…にしては大きめの声で叫んでいるおじいさんがいました。
「よく見てろ!一瞬たりとも見逃すな!」
ちらっとおじいさんの方を見ると、おじいさんは、朝まで飲んでいたのか少し酔っぱらっているような感じに見えます。
おじいさんは壁に取り付けられた大型テレビに、穴があくような鋭い視線を送っています。
つられて僕もテレビを見ました。
水族館の特集でイルカショーの様子が流れています。
「何やってんだ!そこだ!そこで写真を撮るんだ!それがお前たち飼育員の仕事だろ!!」
・・・ちがうよ。苦笑
「よし!そうだ。それでいい!」
え!? 撮ったの???
と、僕は思わず笑いそうになってしまいましたが、決して表情には出さないようにしていました。
それは周囲の他の順番待ちをしている人たちも同じだったようです。
じいさんが少年にあびせた暴言
この病院の出入り口は自動ドアではありませんでした。
一人の患者さんが、診察を終えて会計を済ませ、カラカラとドアを開けて出て行きました。
ドアの一番近いところには、小学4年生くらいの男の子。
そしてその隣にはさっきの独り言のおじいさんが座っていました。
よく見ると、その男の子とおじいさんは顔が似ていると言えなくもありません。
この子の付き添いできたおじいさんなのかな、などとする必要もない推察していたとき、
「……貴様、ドアが開いていることに気づかんわけはあるまい。なぜ何もしない。その頭は飾り物か?貴様に大脳はあるのか。よく考えろ。」
じいさんは、小さい声ながらも凄みのきいた強烈な言葉で男の子に話しかけていました。
しかし、それに無反応な男の子にしびれをきらしたのか、おじいさんは静かに立ち上がり、こう言ったのです。
「その干からびた小さな大脳にも、今のこの現状をどうするべきか分かるはずだ。」
超こわい。
もはや風格は、エドワード・ニューゲート “白ひげ” そのものでした。(尾田栄一郎『ONE PIECE』)

しかし、男の子は完全にノーリアクション。
あえて、じいさんと目を合わせないようにしているのでしょう。
完全に横を向いてしらんぷりしています。
なかなかの神経、いや、じいさんはいつもこんな調子で、孫であるこの子としては、もう慣れているということなのでしょうか。
じいさんの必殺技
「足が動かないというなら、その足は必要のないものだ。俺が切り落としてやろうか・・・」
じいさんは、腕をゆっくり耳の横あたりまで振り上げた。

ちょ、ちょっと待て。
殴るのか?
おいおい!?
僕だけではありません。
待合室の視線を一身に集めたじいさんの背中に、「ちょっと待ってください!」という声が発せられるより早く、じいさんの手刀が斜めに空を切り裂いていきました。
「かまいたち!」
え?
じいさんは、「かまいたち」という掛け声とともに自分の左腰のあたりまで斜めに腕を振り下ろしました。
一瞬の静寂の後、僕の隣にいたおばちゃんが「ぷ」と小さく笑いました。
おばちゃんと目を合わせた僕は、じいさんに気づかれないように顔を少し下に向けながら声を出さずに笑いました。
男の子はさすがに言うこと聞き始めて、無言で立ち上がってドアをしめていました。
「そうだ。それがお前の仕事だ。」
・・・ちがうよ。
じいさんと少年
何にしても待合室はほっとした空気と苦笑いに包まれていました。
しばらくすると、その男の子が名前を呼ばれ、診察室に入っていきました。
つきそいのかまいたちじいさんは、再びテレビにいろいろ小言を言っています。
男の子が診察室から出てきました。
じいさんとは何の会話もしていません。
しばらくすると、男の子は薬をもらって一人で帰っていきました。
Σ( ゚Д゚)・・・えっ!?
じいさん!
あんた、つきそいじゃないの!?
見ず知らずの子に「干からびた小さな大脳」とか…。
もうびっくり。
僕は手で口元を覆いニヤけてしまいそうになる顔を隠していました。
次なるかまいたちじいさんのターゲット
その後、少しずつ空席ができ始めた待合室の中を、じいさんは転々と移動していました。
相変わらず何かブツブツ言っています。
でも僕は、このじいさんは口は悪いものの、特に誰かに危害を加えたりすることはなく、そのあたりの線引きはちゃんとしている人なんだなと思うようになっていました。
そんな思いから、しだいにじいさんが何を言っても僕は気にしなくなっていました。
ですが、僕が雑誌を取り換えて、もともと自分の座っていた位置に戻ったとき、じいさんを気にしないわけにはいかないことが起きたのです。
じいさんが僕の後ろをついてきて、僕の目の前に座ったのです。
あからさまに移動するのも失礼だよなと僕はその場を動かなかったが、僕は別のことに気がついてしまいました。
じいさんは、僕ではなく、僕のとなりにいた赤ちゃんにモンクがあったようなのです。
赤ちゃんは、「わーわー」泣いていて、それがじいさんにはうるさいらしい。
ここは病院なのだから、健診でもないかぎり何か身体に異常があって来ていると思うのです。
その異常を伝える手段が、赤ちゃんには「泣く」ことしかないのだ。
それをテレビの音が聞こえないだの、公共の場での作法がなっていないだのと自己矛盾したことをブツブツ言い始めた。
「黙らないというならその舌を切り落としてやろうか。」
( ゚Д゚)は?
…さすがに僕はイラッときました。
お酒のにおいがしているので、朝まで飲んでいて酔っているのだと思いますが、だからこそ黙っていられませんでした。
じいさんは、また “かまいたちのポーズ” をしています。
おそらくじいさんがこの赤ちゃんに危害を加えることはないでしょう。
でも、いくらなんでもちょっと言いすぎだしやりすぎです。
その赤ちゃんのお母さんは、赤ちゃんを隠すように抱え、何も言い返さずにじいさんに背を向け身を震わせています。
僕しかいない。
この赤ちゃんと、お母さんを救えるのは隣にいる僕しかいないのだ。
僕は雑誌を椅子に置いて、ずいっと立ち上がりました。
「ちょっとやりすぎじゃないですか?」
僕は、じいさんの肩に手を触れると、じいさんはササッと半歩下がり、僕との間合いをとりました。
そして、ゆっくり正面で両腕をクロスしています。
・・・・・・・
来る。
アレが来る。
次の瞬間、じいさんは叫んだ。
「バリア!」
かまいたちじゃねえのかよ。
おわり
それではまた。
エッセイブログの更新通知はこちらから。不定期更新でも見逃しません😚
学習塾カレッジ塾長のXアカウントです。
公私ごちゃまぜでつぶやいています。よかったらフォローしてください😘