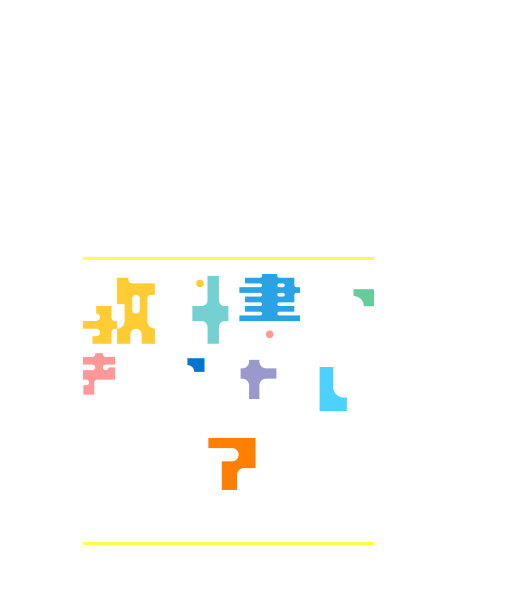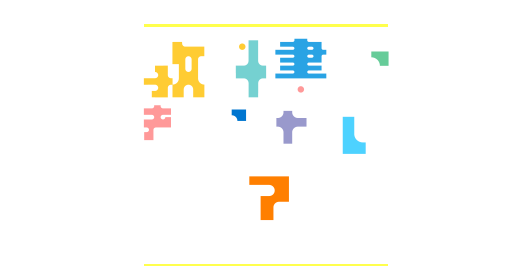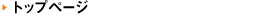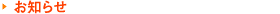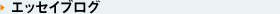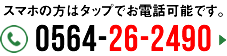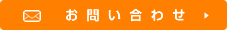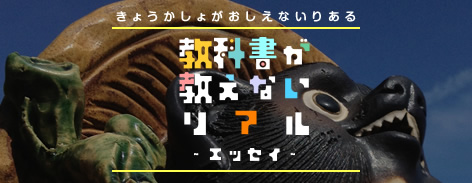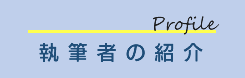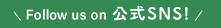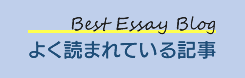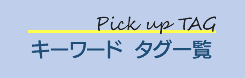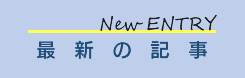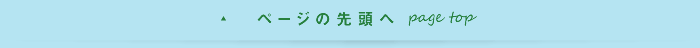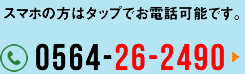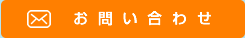29
2018.03
【創作】おとぎ話「ももたろう」の続きを国語の教科書(東京書籍)のパロディで。
小6の課題作文で「ももたろうの続き」をテーマにしたことがあります。
子どもたちのユニークな「続き」を読んでいて、どーにもいてもたってもいられず、僕自身もダダーっと小6国語教科書のパロディ入り物語を書いて子どもたちに披露してしまった思い出が。笑
パソコンの中からそれが出てきたので、少し長いですが、東京書籍の6年の国語の教科書の内容をご存知の方なら楽しんでいただけるのではないかと思います。( *´艸`)
パロディなので、ご存じない方には難しいかも…すみません。
『ももたろう』の続き ―西川の大冒険―
桃太郎は鬼ヶ島からもどったあと村長となり、村一番の美しい娘と結婚して幸せな生活を送っていた。
そんな桃太郎には子どもがいた。
名前は「西川」。
みょうじではない。これが名前なのだ。
体に桃太郎の血が流れているからだろうか、西川は強くたくましい男に成長していった。
村は活気にあふれ、いつも笑顔がたえることはなかった。
虫も鳥も、山から流れてくる小川でさえも、いつも楽しげな歌を歌っているかのようにあたたかさに包まれていた。
そんな幸せな日々が続いていたある日、村全体を震え上がらせる恐ろしい知らせが届いた。
「鬼ヶ島で、桃太郎たちが退治した鬼の子どもたちが、親のかたきを討とうといくさの準備をしているらしい。」

その情報はすぐに村長の桃太郎に届けられた。
「やはり…。」
桃太郎は、すでにこの事態を予想していたかのように落ち着いていたが、その表情はけわしく、みけんには深いしわがたたまれていた。
そして、西川は桃太郎にたずねた。
「父さん、何か知っているの?」
桃太郎はしばらく黙っていたが、覚悟を決めたように西川に話し始めた。
「実はな、鬼ヶ島に鬼退治に行ったとき、鬼の生き残りがいることは知っておったのじゃ。
しかし、その生き残りは、まだ小さな子どもの鬼たちじゃった。
いくら鬼の子ではあっても、小さい子どもを殺すことなどわしらにはできなかったのじゃ。
わしらが鬼ヶ島を去っていくとき、鬼の子どもたちはずっと泣き叫んでおった。
わしには今でもあのときの『パパー!ママー!』と泣き叫ぶ鬼の子どもたちの声が、耳の奥で鳴り響いて離れんのじゃ…。」

隣ですすり泣く母の声だけが小さく響いている。
「お前もきっとわしをひどい奴だと思うじゃろう。…たしかにひどいが、あのときは仕方がなかったんじゃ。
そしていつか、あの鬼の子たちが、親を殺されたうらみを晴らしに来るであろうことは、なんとなく予想しておった。
わしの命はいいんじゃ。仕返しされて当然のことをしたんじゃから。
でもな、西川。わしはこの村をおまえに守ってほしいんじゃ。この美しい自然を。この美しい村人たちの笑顔を守ってほしい。悲しみの涙でゆがんだ顔にしてほしくないんじゃ。」
西川は迷うことなく答えた。
「もちろんさ!おれもこの村が好きだ!この村を守るためなら、おれも父さんと同じ苦しみにたえてみせるよ!」
母のすすり泣きは号泣へと変わっていた。
だが西川は、そのたくましい背中に、母の悲しみさえも背負おうとしていたのである。

こうして、年老いた桃太郎にかわって、西川が鬼ヶ島へ向かうことが決まった。
村の人々だけではない。あらゆる生き物、自然。みんなが西川を心配そうに見つめていた。
大きく息を吸い込んで、そんな村のすべてのものに聞こえるように、まさかの大西ライオンではなく本家ばりの大声で叫んだ。
「し~んぱ~いないさー♪」

・・・完全に空気を読んでいないし、すべっている。
しかし、すべり芸を得意とする西川にはむしろこのすべった空気がたまらない快感であり、旅立ちの祝福のように感じられた。
西川は道を進む。まるで動く歩道を進んでいるときのような軽い足取りだ。
そんなとき、西川の足がピタッと止まった。
「仲間が必要だな…。」
父の桃太郎がサルや犬やキジを仲間にして戦ったことを思い出したのだ。
(時代は進化している。もっと強力な仲間がほしい。)
そう思った西川は、サルにかわるある動物を探した。
いた。
これは意外にもすぐに見つかった。ゴリラだ。サルよりやはりゴリラの方が強いだろう。
「おい、おれの仲間になってくれ。」
西川がゴリラに言うと、くるっとふりむいてゴリラがこたえた。
「あら、あたしのこと誘ってるの?」

なんと予想外にもゴリラはメスだった。西川は(しまった…)と思ったが、どうせ断られるだろうから問題ないやと軽く考えた。
「ああ。いやならいいんだけど…。」
「全然いやじゃないわよぅ。あたし、ミコっていうの。ちょうどあたしも探している人がいるの。一緒に行きましょ!」
なんとなく不本意だったが、ゴリラが仲間になった。
西川が船の出港準備をしている間に、ゴリラのミコに他の仲間探しを頼んだ。
『キジより強そうなタカ。犬より強そうなオオカミ。』
これが西川の注文だった。
しかし、ミコが連れて来たのはタカではなくツル。オオカミではなくネズミ二匹だった。
「(おいおい!全然ちがうじゃねえかよ!)」
ツルとネズミに聞こえないように、西川はミコに言った。
「(大丈夫よ。あたしの見る目にまちがいはないから。)」
「(ツルはともかく、ネズミはないだろ~!?)」
ゴリラのミコは、西川のモンクを聞く気もない様子で、話を変えた。
「あっ、そういえばまだ名前を聞いていなかったわね。」
すると、ツルがぼそっと小さい声で言った。
「…おれはクルル。カララっていう親友と一緒に飛んでいたんだけど、おいてけぼりにされたんだ。」
続いて、ネズミが言った。
「ぼくらはネズミに見えるけど、ラットの夫婦。何でも食べるこの前歯がぼくらの自慢さ。『チーム西川』の結成だな!はりきって行こうぜ!」
ラット夫婦のはじける笑顔と、どこかくもった表情のクルルを仲間に加え、いよいよ船は出港した。
波の奏でる音楽に合わせて、チーム西川は踊るように船をこぎ進めていった。
そして、お日さまに十回目のあいさつをしたとき、ついに目的の鬼ヶ島にたどりついた。
ていさつに行っていたクルルがもどってきた。
「何か大きな石がいっぱい置いてあるぞ。あれは監視用の建物かもしれない。」
「よし、あのでかい石に気をつけて、上陸作戦開始だ!」
「おおー!」
みんなが声を合わせた。
島に上陸し、クルルの言っていた「大きな石」を見て、みんなあぜんとした。
巨大な石は「顔の形」をしていた。
そして、予想よりはるかにたくさんあった。高さが三メートルから十メートルもあり、重さは三トンから十トンにもおよぶ。中には、高さ二十メートル、重さ五十トンに達するものまである。

「いったいこれは何なんだ。」
みんなが不思議そうに思っていると、ラット夫婦が突然走り出した。
「あっ逃げやがった!!」
でも、長い船旅の末、ようやくこの島にたどりついた一行にとって、彼らの逃走など、ほんのささいな出来事でしかなく、みんな追いかけようとはしなかった。どうせ鬼退治には戦力にならない。
自分の見る目にまちがいはないと言っていたミコは、(知~らんぺ~♪)とでも言いたそうに口笛を吹いてごまかしている。
しばらく歩いていると、ミコが島の地図を見つけてきた。
地図には「イースター島」と書かれている。
これが鬼ヶ島の本当の名前か…。
みんな少し驚いていた。地図には、この島のメインの城らしき建物の場所がかかれていた。
この城に鬼たちがいるにちがいない。みんなは、武器をにぎりしめ、その場所へ向かった。
「しかしこれだけ森林がなくて、どうやってあの石像を運んだんだ?」
「鬼が持ち上げたんだよ。すげえ力持ちにちがいないな。…ゴクッ。」
ギラギラと照りつける太陽が、これから始まる戦いの苦しさを物語っているかのようだった。
「鬼たちはあそこにいる!」
ついに鬼の城へたどりついたチーム西川(一部脱走中)は、目を丸くした。
「…こ、これが城なのか?」
荒れ果てた大地、壊れた屋根にひびだらけの柱。目の前にある城…と思われる建物は、もはや廃墟に近かった。
「あっ!あれを見て!」
ミコが叫んだ。
今にもくずれそうな建物の中に五、六人の人影が見えたのだ。
「あれが…鬼?」
クルルがポカンとした表情でつぶやいた。西川も言葉を失っている。
鬼というには、角もなく、がっちりした体格どころか、むしろ骨と皮だけのようなガリガリの体。
それに若い鬼というより、なんとなく年寄りばかりだ。
もはやチーム西川も、武器を手から離していた。
「ちょっと話を聞きに行こう。何が何だかわからないよ。」
西川が言うと、ミコとクルルはだまってうなずいた。
「あの…すみません。ここは鬼ヶ島…ですか? 失礼ですが、あなたたちは鬼なんですか?」
西川が話しかけると、目の前にいた人たちがゆっくりと集まってきて、話をし始めた。
「鬼か…。わしらは、鬼じゃないよ。わしらがここに初めて来たころには、小さい鬼が何人かおったが、むごいことをしたもんじゃ…。わしらが全滅させてしまった。
わしらはな、ポリネシア人というんじゃ。かつてはこの島も人も豊かな生活を送っておったが、自然の利用方法を誤って、今じゃこんなありさまじゃよ。」
西川は驚きをかくせない様子で、質問を重ねた。
「そんな!この島でいくさの準備をしていると聞いたんですが!?」
別の年老いたポリネシア人が口を開いた。
「いくさというか、狩りの準備じゃな。
この島に豊かに生いしげっておったヤシの木の種を食べつくしたラットというネズミを滅ぼさんことには、この島はもう永遠に木が生えてこんのじゃ。
だから、わしらの最後の生き残る手段として、ラット全滅作戦を決行しておったのじゃよ。
愚かじゃろう。自分たちが生きるために、他の生き物を滅ぼすことをくり返す。わしらは本当に愚かな生き物じゃ…。
じゃが、それももう終わった。
もうこれからは自然を大切に、生き物の命を奪うことなく、心おだやかにいきてゆくよ。」
「そうだったんですか・・・。」
ふと気がつくと、ミコがブルブルと震えている。その視線の先には、もう一匹の別のゴリラがいた。
「あぁ、あれか。あれはわしらのペットのゴリラじゃ。あれもだいぶ年をとって、目が見えんようになってしもうたがね。むかし生き別れた子どものゴリラをずっと心配しておるんじゃ。」
ポリネシア人がそう言うと、西川はハッとした。
「ミコ!もしかしておまえが探している人って!?」
そう西川が言い終わるよりも早く、ミコは、そのゴリラのところへ走っていった。目からは涙があふれ、こぼれ落ちるしずくが無数の宝石のようにきらきらと輝いている。
ミコがギュッとそのゴリラを抱きしめると、その感触からすぐに自分の子どもであることを感じたのか、母ゴリラはミコの顔や頭をさわり、
「ミーちゃん、ミーちゃん、あんた、ミコちゃんよねえ。」と何度も確かめていた。

西川は、「しっかりするんだ。お母さん、しっかりしなきゃ・・・!」と叫んだ。
すると母ゴリラが言った。
「うるさいね!あたしゃしっかりしてるよ!!感動の再会をじゃましないでおくれよ!」
西川は母ゴリラに怒られた。まだまだこのゴリラは長生きしそうだ。
そして、ミコはこのままこの島で母ゴリラと暮らすことになった。
何はともあれ、いくさの情報が勘違いだったことを知った西川は、はやく村に帰ってこのことをみんなに教えてやろうと船を出した。
船をこいでいる途中で、クルルの目に、南の空からまい降りてくる一羽の鳥が見えた。
カララだ。
カララは何も言わずにクルルのとなりに降り立った。
クルルはカララと一緒に飛び立とうと思っていたが、西川に気をつかったのか、船を離れようとしない。
日に日に暑さが増してくる。熱中症寸前である。(そうか、おれが飛ばないとこいつも…。)とクルルが思った、そのとき!西川がクルルに声をかけた。
「ははは、いいよ。あとはおれ一人で帰るから。一緒に行けよ!今度ははぐれないようにな!」
「ありがとう!」
どこかくもりがちだったクルルの表情に明るさがもどってきた。バサバサとはばたくクルルの翼から、羽毛がひらひらと雪のように舞い降りてきて、西川の手におさまった。

「ああ、みんな元気でな…。これにて、めでたしめでたしだ。」
そうつぶやきながら、西川は、船の上で横になり、どこまでも広く、深い青色で澄み渡った空を見上げていた。
すると、ネズミの形をした雲がふわふわと浮いているのを見つけた。
「Σ(; ・`д・´)あぁっ!!」
西川は、重大なことを忘れていたことに気がついた。
「あのポリネシア人たち、ラットを全滅させて、もう二度と生き物は殺さないって言ってたけど…。
おれたちがラット夫婦を脱走させたままだった。
どどどど、どうしよう!」
―数ヵ月後。
世界新聞にこんな記事が載った。
『ポリネシア人、無念。…全滅させたはずのラット、再び現れる。』
完
エッセイブログの更新通知はこちらから。不定期更新でも見逃しません😚
学習塾カレッジ塾長のXアカウントです。
公私ごちゃまぜでつぶやいています。よかったらフォローしてください😘